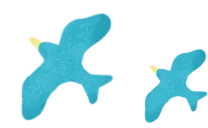
臭い・水処理 用語集
臭い用語一覧
臭いのことに関わる用語をご紹介します。
>> 水処理用語一覧 <<
-
悪臭
不快なにおいのこと。公害の一種として規制されることがある。
-
臭気
におい一般を指す言葉で、良い香りも悪臭も含む。
-
悪臭公害
悪臭によって生活環境が損なわれる被害のこと。
-
悪臭防止法
悪臭による公害を防ぐための日本の法律。
-
特定悪臭物質
悪臭防止法で規制される22種類の悪臭原因物質。
-
アンモニア
刺激の強いアルカリ性の気体で、し尿のような臭いを持つ。
-
硫化水素
腐った卵のような臭いをもつ無色の有毒気体。
-
メチルメルカプタン
腐ったタマネギのような強い悪臭を放つ有機硫黄化合物。
-
トリメチルアミン
魚が腐敗したような生臭い臭気を持つ有機窒素化合物。
-
アセトアルデヒド
刺激的で青臭いにおいを持つ揮発性液体。
-
スチレン
プラスチックの原料で、甘いような独特の臭いを放つ。
-
酢酸エチル
シンナーや接着剤のような刺激臭をもつ有機溶剤。
-
トルエン
ガソリンに似た臭いをもつ芳香族炭化水素。
-
キシレン
トルエンに似たガソリン様の臭いを持つ芳香族炭化水素。
-
酪酸
腐ったバターのような悪臭をもつ有機酸。
-
インドール
糞便臭や腐敗臭の原因となる有機化合物。
-
臭気指数
臭気の強さを数値化した指標で、臭気濃度の対数値を用いる。
-
臭気濃度
臭気を希釈して無臭になるまでの希釈倍数。
-
臭気強度
人が感じる臭いの強さを0~5の6段階で評価する指標。
-
嗅覚測定法
人の嗅覚を使って臭気を測定する方法。
-
三点比較式臭袋法
悪臭防止法で定められた臭気指数の測定方法。
-
臭気判定士
臭気測定の専門資格を持つ技術者。
-
ニオイセンサー
臭気成分を検知して数値化する電子機器。
-
吸着法
活性炭などに臭気成分を吸着させて除去する方法。
-
燃焼法
臭気物質を高温で燃焼し、無臭の物質に分解する方法。
-
生物脱臭
微生物の働きを利用して臭気成分を分解する脱臭方法。
-
オゾン脱臭
オゾンを用いて臭気成分を酸化・分解する方法。
-
光触媒
光エネルギーで臭気を酸化分解する触媒技術。
-
脱臭装置
悪臭を除去または低減するための機械装置の総称。
-
スクラバー
臭気を薬液で洗浄して除去する装置。
-
バイオフィルター
微生物が繁殖した充填材を通して臭気を分解する装置。
-
活性炭
臭気成分を吸着するための炭素質の多孔質材料。
-
ゼオライト
臭気分子を選択的に吸着する多孔質鉱物。
-
消臭剤
悪臭を消すための薬剤や製品の総称。
-
芳香剤
良い香りを発散させて空間の臭気を快適にする製品。
水処理用語一覧
水処理に関わる用語をご紹介します。
>> 臭い用語一覧 <<
-
BOD(生物化学的酸素要求量)
水中の有機物が微生物によって分解される際に消費される酸素の量を示す指標。
-
COD(化学的酸素要求量)
水中の有機物を酸化剤で化学的に分解するのに要する酸素量を示す指標。
-
SS(懸濁物質)
水中に浮遊して水を濁らせている固形の不溶解性物質の量(濃度)。
-
T-N
水中に含まれる全ての窒素成分の量(無機性窒素+有機性窒素の合計)。
-
T-P
水中に含まれる全てのリン成分の量(無機リン+有機リンの合計)。
-
富栄養化
湖沼や海などの水域で窒素やリンが過剰に蓄積し、藻類が異常繁殖する現象。
-
標準活性汚泥処理法
微生物の塊である活性汚泥を利用し、有機物を分解して汚水を浄化する方式。
-
嫌気無酸素好気法(A2O法)
下水中のリンと窒素を同時に除去するため、嫌気→無酸素→好気の順に処理する方式。
-
MBR(膜分離活性汚泥法)
膜による固液分離を利用した活性汚泥処理方式で、従来の沈殿槽の代わりにろ過膜を使用。
-
浄化槽
下水道が整備されていない地域で家庭の汚水を個別に処理する装置。
-
沈砂池
下水処理場に流入した汚水中の大きなごみや砂粒を最初に沈降・除去する池。
-
最初沈殿池
下水中の浮遊固形物を生物処理の前段階で沈降させる沈殿池。
-
最終沈殿池
生物処理で生成した活性汚泥を沈降分離し、清澄な処理水を得るための池。
-
反応槽
下水と活性汚泥を空気とともに攪拌し、微生物の働きで有機物や窒素を分解・除去する槽。
-
散気管
曝気槽に空気を吹き込む際に細かい気泡を発生させ、水への酸素溶解効率を高める装置。
-
ブロワ
下水処理の曝気槽に空気を送り込むための送風機械。
-
加圧浮上法
水中の油分や浮遊物を加圧溶解した空気の気泡で浮上させて分離除去する処理方法。
-
凝集沈殿法
薬品の添加によって微細な浮遊物をフロック状に凝集させ、沈降分離する水処理方法。
-
大腸菌群
人や動物の糞便に由来する汚染の指標となる細菌群。
-
界面活性剤
水と油を混ざりやすくする性質を持つ化合物の総称で、洗剤などに含まれる。
-
油分
排水中に含まれる動植物油や鉱物油などの油脂成分。
-
易分解性
有機物が微生物によって比較的容易に分解・処理できる性質。
-
難分解性
有機化合物が微生物によって分解されにくい性質。
-
栄養塩
排水中の微生物が増殖・代謝するために必要な栄養元素(主に窒素とリン)。
-
バルキング
活性汚泥の凝集性・沈降性が悪化し、汚泥が膨張して沈殿分離できなくなる現象。
-
糸状菌
糸状の形態を持つ細長い細菌の総称で、活性汚泥の沈降性を悪化させる原因となる。
-
発泡
活性汚泥処理において曝気槽や処理水面に大量の泡が発生する現象。
-
負荷変動
過負荷…排水中の汚濁負荷が処理設備の処理能力を超えて流入し続けている状態。
低負荷…排水の汚濁負荷が処理能力より低い状態で推移し、その結果として活性汚泥の状態が不調になる現象。 -
硝化
アンモニア性窒素が微生物の作用によって亜硝酸塩や硝酸塩に酸化される反応。
-
脱窒
硝酸態窒素や亜硝酸態窒素が嫌気性条件下で窒素ガスに還元され、大気中へ除去される現象。
-
汚泥
下水処理場や産業排水処理施設から発生する泥状の排出物の総称。
-
汚泥脱水
汚泥の含む水分を機械的に絞り出して減らし、汚泥を固形状に濃縮する処理工程。
-
焼却
脱水汚泥などを高温炉で燃焼させ、有機物を灰化させて汚泥量を大幅に減容する処理方法。
-
堆肥化
汚泥におがくず等を混ぜて好気的に発酵させ、堆肥(コンポスト)にする再利用処理。
-
メタン発酵
汚泥を酸素の無い条件下で発酵させ、有機物を分解しメタンガスを生成する処理。
-
消化ガス
嫌気性消化によって汚泥から生成される可燃性のガスで、主成分はメタンと二酸化炭素。




