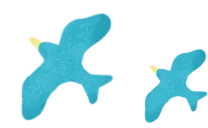

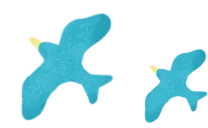

(公開日:2025年4月14日)
悪臭防止法は、生活環境を保全するために事業活動から生じる悪臭を規制する法律として、1972年に制定されました。近年は飲食店やサービス業、食品製造工場など都市型の悪臭発生源の割合が高まっており、公害苦情全体の中でも悪臭トラブルが上位を占める状況が続いています。
環境省の調査では、令和元年度の悪臭苦情件数が12,020件にのぼり、前年度から696件増加しています。感覚公害の一種である悪臭は個人差や気象条件などの多様な要因が絡むため、対策には慎重で実務的な知識が求められます。
この記事では、悪臭防止法の枠組みや規制基準の数値、法令違反を防ぐための対策、苦情対応の流れなどを解説します。
悪臭防止法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、生活環境を保全し、国民の健康保護に資することを目的として制定された法律です。1971年(昭和46年)6月に公布され、数度の改正を経て現在に至っています。
悪臭防止法の特徴として、国は法律で基本的な枠組みを定め、実際の規制基準の設定や規制の実施は地方自治体が行う仕組みになっています。これにより、地域の実情に合わせた柔軟な対応が可能となっています。
悪臭防止法では、規制方式として以下の2つの方法があります。
近年は臭気指数規制方式を採用する自治体が増加傾向にあります。これは飲食店や小規模事業場などから発生する複合的な臭いに対応する必要性が高まっているためです。
悪臭の強さを評価する方法の一つに「六段階臭気強度表示法」があります。六段階臭気強度表示法は、臭いの強さを0(無臭)から5(強烈な臭い)までの6段階で評価する方法です。
| 臭気強度 | 臭いの強さ |
| 0 | 無臭 |
| 1 | やっと感知できる臭い |
| 2 | やっとなんの臭いかがわかる程度の臭い |
| 3 | らくに感知できる臭い |
| 4 | 強い臭い |
| 5 | 強烈な臭い |
臭気強度2.5〜3.5が敷地境界線上の規制基準の範囲であり、臭気強度と上で紹介した臭気指数の関係は以下のようになっています。
つまり臭気指数10〜21が規制基準の範囲であり、一般的に臭気強度2.5、臭気指数10(やや強い臭い)を下回るレベルが生活環境を保全する上での目安とされています。
悪臭防止法に基づく規制基準は、各自治体が地域の実情に応じて設定するため、まずは事業所が立地する自治体(都道府県または市区町村)の環境部局に確認することが重要です。
悪臭防止法では、以下3種類の規制基準が定められています:
規制地域は主に以下のような区分に分けられます。
各区域によって規制基準値は異なり、一般的に第一種区域ほど厳しい基準が適用されます。
規制基準を確認する際のポイントは以下の通りです。
これらの情報は自治体のホームページで公開されていることが多いですが、不明な点は環境部局など自治体の担当部署に直接問い合わせるのが確実です。
悪臭防止法に関する詳細情報として、以下の環境省および関連団体が発行する資料が参考になります。リンク先の内容をご参照ください(すべて出典明記のもとで引用可能な公的資料です)。
焼き鳥店の排気ダクトから排出される煙と臭いが近隣マンションの居住者から苦情の対象となりました。排気口がマンションの窓に近い位置にあり、風向きによっては強い臭いが室内に入り込む状況でした。
この苦情に対し以下の対応を行い、煙の視認性が大幅に低下。臭いもほとんど感じられないレベルまで改善されました。
苦情は解消され、営業を継続できています。
印刷工場から排出される有機溶剤の臭いが周辺住民から苦情となりました。臭気測定の結果、敷地境界での臭気指数が規制基準を超過していることが判明。
この苦情に対し以下の対応を行い、対策後の測定では臭気指数が基準値以下となり、周辺住民からの苦情も減少しました。
定期的なモニタリングと装置のメンテナンスを継続することで安定した状態を維持しています。
食品製造工場でにんにくを使用する工程から発生する臭いが問題となり、排気口からの臭気濃度が基準値を超過していました。
この苦情に対し以下の対応により臭気発生源を根本から削減することに成功し、基準値を満たすことができました。
工程変更コスト増は発生したものの、近隣との関係改善というメリットの方が大きいと判断されました。
悪臭防止法における規制基準や必要な対策は自治体ごとに異なるため、事業所が所在する地域の自治体が公開している情報を確認することが重要です。
特に確認すべき情報としては以下の通りです。
これらの情報は自治体のホームページで公開されていることが多いですが、不明な点があれば環境課などの担当部署に問い合わせることをおすすめします。
既に悪臭問題を抱えている、あるいは予防的な対策を検討している事業者様は、悪臭対策の専門企業への相談も有効な選択肢です。無臭元では、60年以上にわたる豊富な実績と知見を活かし、多種多様な悪臭問題に対応した解決策を提供しています。
悪臭問題は、発生してからの対応では周辺住民との関係悪化や対策コスト増を招く可能性があり、予防的な対策を実施することが理想ですが、臭気トラブルが発生した場合には初期段階での適切な対応が重要になります。
専門家の知見を活用し、効果的かつ経済的な臭気対策を実施することで、事業の安定的な継続と良好な地域関係の構築が可能となります。
臭気対策でお悩みの際は、無臭元までお気軽にご相談ください。現場の状況に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。