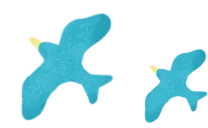

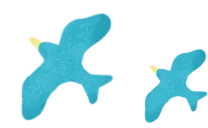

(公開日:2025年4月24日)
下水管路は家庭や事業所から排出される生活排水・汚水を、下水処理場へ送る重要な生活インフラです。その一方で、下水管路内では嫌気状態が形成されやすく、硫化水素(H₂S)などの危険性ガスが発生する場合があります。これらのガスが、下水管路内に滞留したり、マンホールや排水口から漏れ出すことで、地域住民にとって大きな不快要因となるだけでなく、健康リスクや下水管路のコンクリート腐食による水漏れや道路などの地盤陥没事故の発生など深刻な事態を引き起こす可能性があります。
関連記事:悪臭防止法とは?規制基準や対策方法、改善事例も紹介
下水処理場は、全国に約2,200箇所あり、下水道管路の総延長は約49万kmに及んでおり、全国各地至るところに管路は存在しています。生活に身近なインフラであり、ひとたび臭気問題が発生すると地域のイメージダウンや生活環境への不満に繋がる恐れがあります。
また、硫化水素によるコンクリート腐食のリスクが顕在化すると、多くの地域住民の生活に影響が出ることはもちろん、補修や交換に巨額のコストがかかる懸念もあり、自治体や事業者にとって大きな課題となります。
この記事では下水管路(マンホール)から硫化水素などの臭いが発生する原因や臭気の対策方法について解説します。
下水管路やマンホールから発生する臭気の主原因は硫化水素です。この硫化水素がどのように発生するのか、その主な原因を詳しく見ていきましょう。
下水管路内では、汚水に含まれる有機物が微生物によって分解されます。酸素が少ない環境(嫌気状態)では、嫌気性菌(通性嫌気性菌、偏性嫌気性菌)などの微生物が活性化します。特に硫酸還元菌は、酸素の代わりに硫酸塩(SO₄²⁻)を利用して有機物を分解する過程で硫化水素を発生させます。
この現象は特に以下の条件で起こりやすくなります。
工場排水や事業所からの排水には、すでに硫化水素や硫化物を含む場合があります。たとえば、以下のような事業所からの排水は注意が必要です。
これらの排水が下水管路に流入すると、既存の硫化物が酸性環境で硫化水素として放出されることがあります。
管路の構造上の理由で有機物が堆積したり、家庭や飲食店から流される油脂や食物残渣が下水管路内に蓄積すると、これらが微生物によって分解される過程で悪臭が発生します。特に問題となるのは以下の要因です。
これらの原因が複合的に作用することで、下水管路内の硫化水素濃度が上昇し、マンホールや通気口から臭気が漏れ出す結果となります。特に「悪臭防止法」で規制対象となっている硫化水素は、その特有の「腐った卵」のような臭いで、非常に低濃度(0.00041ppm程度)でも人間が感知できるため、わずかな漏出でも苦情の原因となる可能性があります。
硫化水素の発生は単に臭気問題だけでなく、さまざまな深刻なトラブルや事故の原因となります。以下に代表的な事例を紹介します。
硫化水素は極めて有毒なガスであり、濃度によって以下のような健康被害をもたらします。
実際、日本国内でも硫化水素による中毒事故が発生しています。たとえば、2025年3月、マンホール内で下水道管の取り替え工事を行っていた作業員3名が、硫化水素中毒と思われる症状により死亡する事故が発生しました。これまでも、下水道作業中に硫化水素中毒による死亡事故が数多く報告されており、このような事故は適切な安全対策が講じられない場合に繰り返される危険性があります。
下水管路からの臭気は、住民生活の質に直接影響を与え、自治体への苦情の大きな原因となります。
環境省の調査によると、悪臭に関する苦情は年間約13,000件あり、下水道に関連する苦情も少なくありません。特に夏季や気温の高い時期には苦情が集中し、自治体の対応負担が増大します。一度苦情が発生すると、問題解決までに相当の時間とコストがかかることが多く、自治体のイメージダウンにもつながります。
2011年の東日本大震災時において、下水道施設が大きな被害を受け、深刻な臭気問題が発生した自治体の事例があります。地域の広範囲で下水道管が破損し、約500ヘクタールの範囲で排水不良が発生しました。
被災直後、行政は緊急対策として滅菌処理した汚水を河川へ直接放流せざるを得ない状況となりました。しかし、この措置により周辺住宅街で強い臭気が発生し、硫化水素等の危険性ガスによる安全上の問題も生じました。
この時は、無臭元が行政から依頼を受け、消臭剤を用いた臭気対策ソリューションの提供を行い、硫化水素等の臭気の低減に成功し、周辺環境の改善を支援させていただきました。
下水管路やマンホールなど様々な現場で発生する硫化水素による臭気問題には、効果的な対策が必要です。実用的な対策と薬剤の活用について紹介します。
硫化水素対策に使用可能な製品例と薬剤の効果や使用例について紹介します。
| 製品例 | 効果・特長 | 使用例・適用場所 |
|---|---|---|
| ・無臭元AF010-SZ ・無臭元SD ・無臭元アルファー50D ・ムシュウゲンLY-X | ・管路内の硫化水素生成抑制 ・下流施設への影響軽減 ・反応が迅速で効果が即時に現れる ・長期的な効果が期待できる | ・ポンプ場から添加 |
| ・無臭元消臭シートK230 | ・複合臭にも効果を発揮 ・幅広い用途に適用可能 | ・臭気発生の要因となっている対象物に覆い被せる ・動力不要で使用できる |
| ・ムシュウゲンAB095-SC | ・臭気発生している対象エリアに噴霧 | |
| ・ラバトリアンWP ・ラバトリアンWPF | ・緊急時の硫化水素などの臭気対策 ・動力不要で使用できる | |
| ・無臭元P014-UZ(顆粒) | ・環境に及ぼす影響が極めて低い ・徐放作用があり、長期間の効果の持続が期待できる | ・簡易放流時に河川へ直接添加 ・側溝や下水流入などの汚水に添加 |
効果的な臭気対策には、精度の高い測定・評価が欠かせません。主な方法には以下があります。
効果的な対策実施のためには、対策前後での測定結果の比較が重要です。特に、薬剤添加前後の硫化水素濃度変化や臭気指数の改善度を確認することで、対策効果を客観的に評価できます。
下水管路やマンホールからの臭気問題は、放置すると住民の生活環境悪化や施設の劣化につながる重大な課題です。しかし適切な対策を講じることで、効果的に問題の解決が可能です。
無臭元では、60年以上にわたる臭気対策の専門知識と実績を活かし、お客さまの臭気問題を解決するためのトータルサポートを提供しています。
下水管路やマンホールの臭気でお悩みの方は、ぜひ無臭元までご相談ください。