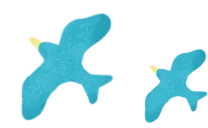

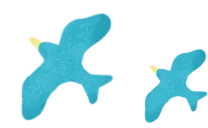

(公開日:2025年9月2日)
工場をはじめとする各種事業場などから発生する悪臭は、近隣住民からの苦情や行政の指導につながることがあり、対応を誤ると事業継続にも影響を及ぼしかねません。中でも、悪臭防止法で規制対象となっている「特定悪臭物質(22物質)」は、対策の要となる重要なポイントです。
万が一、「特定悪臭物質」への対応を怠ってしまった場合、思わぬトラブルや法令違反を招くリスクがあります。地域と良好な関係を保ちつつ、安定した操業を続けていくためには、これらの物質がどのようなものなのかを正しく把握し、適切に対処していくことが欠かせません。
本記事では、特定悪臭物質の基本的な知識から具体的な対策まで、わかりやすく解説します。
特定悪臭物質とは、悪臭防止法 第2条において「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるもの」として指定されている化学物質です。現在、22種類の物質が特定悪臭物質として法的に規制の対象となっており、これらは工場や事業所から発生する悪臭の主な原因だとされています。
悪臭は騒音・振動に次いで公害事象の第3番目に苦情の多い問題であり、令和5年度は11,735件の悪臭苦情が全国で発生しており、そのうち4,171件が工場・事業場にかかる苦情でした(参考:総務省「令和元年度公害苦情調査」、環境省「令和5年度悪臭防止法等施行状況調査の結果について」)。
この問題は郊外・都市部を問わず、また事業者の規模に関係なく発生する可能性があります。「うちは地方だから・小規模事業者だから大丈夫だろう」と考えるのではなく、すべての事業者が適切に対応する必要があります。
特定悪臭物質の詳細な一覧は以下の通りです。
| 分類 | 物質名 | 臭いの特徴 | 敷地境界線の基準 | 主な発生源・発生しやすい場所 |
|---|---|---|---|---|
硫黄系化合物 | アンモニア | し尿のような臭い | 1ppm | 畜産業、下水処理場、し尿処理施設、化製場、ごみ処理場 |
硫化水素 | 腐った卵のような臭い | 0.02ppm | 下水処理場、化製場、食品工場、畜産業 | |
メチルメルカプタン | 腐った玉ネギのような臭い | 0.002ppm | パルプ・製紙工場、し尿処理施設、下水処理場 | |
硫化メチル | 腐ったキャベツのような臭い | 0.01ppm | パルプ・製紙工場、化製場、魚腸骨処理場 | |
二硫化メチル | 強い硫黄臭 | 0.009ppm | ||
窒素系化合物 | トリメチルアミン | 腐った魚のような臭い | 0.005ppm | 水産加工場、肥料製造業、畜産業 |
アルデヒド系化合物 | アセトアルデヒド | 刺激的な青臭い臭い | 0.05ppm | たばこ製造工場、酢酸製造工場、肥料製造工場 |
プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | 0.05ppm | 塗装工場、自動車修理工場、製薬工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食品工場 | |
ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な臭い | 0.009ppm | ||
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | |||
ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | 0.009ppm | ||
イソバレルアルデヒド | 刺激的な臭い | 0.003ppm | ||
アルコール・ケトン系化合物 | イソブタノール | 刺激的な発酵した臭い | 0.9ppm | 木工工場、鋳物工場、塗装工場 |
酢酸エチル | 刺激的なシンナーのような臭い | 3ppm | 塗装工場、印刷工場、木工工場 | |
メチルイソブチルケトン | 刺激的な溶剤臭 | 1ppm | ||
芳香族化合物 | トルエン | ガソリンのような臭い | 10ppm | 塗装工場、印刷工場、繊維工場 |
キシレン | 1ppm | |||
スチレン | 都市ガスのような臭い | 0.4ppm | ポリスチレン製造工場、化粧合板製造工場、FRP製品製造工場 | |
有機酸系化合物 | プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱい臭い | 0.03ppm | 脂肪酸製造工場、染色工場、化製場 |
ノルマル酪酸 | 汗くさい臭い | 0.001ppm | 畜産農場、廃棄物処分場、化製場 | |
ノルマル吉草酸 | むれた靴下のような臭い | 0.0009ppm | 畜産農場、廃棄物処分場、でんぷん工場 | |
イソ吉草酸 | 足のような臭い | 0.001ppm |
これらの物質は、低濃度でも強い悪臭を発し、健康や周辺環境に悪影響を与える危険性があります。とくに密閉された空間での高濃度暴露は、頭痛やめまい、呼吸器への刺激などの急性症状を引き起こす可能性があるため、適切な管理が欠かせません。
悪臭防止法では、排出規制の対象として「臭気指数」および「特定悪臭物質」の2つの基準を設けています。この2つの規制方式により、“科学的な物質濃度管理”と“実際の嗅覚による影響評価”の両面から悪臭問題へ対応しています。
関連記事:悪臭防止法とは?規制基準や対策方法、改善事例も紹介
特定悪臭物質については、物質ごとに敷地境界線における濃度基準値が設定されており、この基準値を超える排出は法律違反です。規制基準値は、6段階臭気強度表示法による「臭気強度2.5~3.5」に対応する物質濃度として設定されています。
臭気指数による規制は、人間の嗅覚を用いた官能試験によって測定される基準で、一般的に10〜21の範囲で設定されます。「臭気強度2.5から3.5」に対応する「臭気指数(6段階臭気強度表示法)」は、次のとおりです。
臭気強度 | 2.5 | 3.5 |
臭気指数 | 10~15 | 12~18 |
なお、特定悪臭物質の具体的な基準値は、各地方自治体が「臭気強度2.5〜3.5」に対応する濃度範囲(上表)を参考に定めており、地域の実情に応じて異なる数値が適用されます。一般地域と工業地域などの順応地域では、異なる基準値が適用される場合がある点を押さえておきましょう。
悪臭防止法を遵守するため、事業者には以下の基本的な対応が求められます。
規制基準を遵守すること
悪臭を伴う事故が発生した場合、直ちに管轄する行政窓口(環境担当部署)に通報し、応急措置を講じること
市町村長からの報告徴収や立入検査に協力すること
第一に、事業者は設定された基準値・臭気指数基準値を常に下回る状態を維持しなければいけません。さらに、自治体の条例や方針により、悪臭を発生させる可能性のある事業開始前や設備変更時に、役所への報告が求められることもあります。
また、悪臭防止法以外にも、下水道法や労働安全衛生法、大気汚染防止法などの関連法規に関わる可能性がある点にも注意しましょう。まずは、事業所が所在する自治体の詳しい規制内容を確認することが大切です。
上記の基本を理解したうえで、臭気を発生させないように以下のような対応を日常的に行いましょう。
各プロセスのポイントを紹介します。
まずは、自社の事業活動から発生する可能性のある特定悪臭物質を特定し、定期的に測定して規制基準を超えていないかを確認しましょう。基準値を超える物質が検出された場合は、まずは原因の特定と応急処置などの緊急対応を優先し、その後、再発を防ぐために、薬剤の使用や設備の見直し、運用改善など、恒常的な対策を計画的に進めましょう。
また製造工程や原材料を変更するときは、新たな悪臭物質が発生する可能性がないか事前に確認しておきましょう。適切な対策を講じていることを示す証拠として、測定データや対策実施状況を記録に残しておくと安心です。
必要に応じて専門業者による臭気測定を実施し、測定結果にもとづいて具体的な対策を計画します。状況によっては、設備の見直しや処理フローの改善に加え、薬剤を活用した機動的な対応を取り入れることも効果的です。
この際、対策の優先順位を明確にして、短期・中期・長期の3つの時間軸で対策プランを策定しましょう。また、投資コストと効果のバランスを考慮し、自社にとって最も効率的な対策方法を見極めることも重要です。
悪臭問題に対応するための責任者を明確にし、従業員への教育・訓練を定期的に実施します。基本的な知識や予防策についてだけではなく、緊急時の連絡体制や対応フローも整備しておくことが大切です。
従業員が悪臭の発生源や対策方法について理解を深められれば、日常業務での予防意識が向上します。定期的な社内点検やチェックリストなどを活用して、問題の早期発見や未然防止に努めましょう。
地域との良好な関係維持は、事業継続において不可欠な要素です。悪臭に関する苦情や問い合わせに対して、迅速かつ適切に対応する体制を整備しておきましょう。
また、臭気モニタリングの導入により、においの状況を数値で把握できるようになるため、住民とのコミュニケーションや苦情対応の根拠としても有効です。苦情が発生した場合には、その内容を記録し、改善措置と結果を苦情者や住民に説明することで、信頼の早期回復につなげられます。
特定悪臭物質への対策には、以下の3つのアプローチがあります。
発生源から対策する
排出経路で対策する
消臭処理技術を活用する
それぞれの代表的な手段を紹介します。
発生源から対策することは、最も効果的で根本的な解決方法です。そもそも事業者には「規制基準を遵守すること」が求められているため、発生源対策の実施は不可欠であるといえます。
無臭元では、発生物質別・発生場所別に応じた対応方法の提案を強みとしており、現場ごとの状況に適した発生源対策を提供します。
たとえば、以下のような対策が有効です。
悪臭の原因物質を多く含む原材料の使用の見直し・切り替えを検討する
反応槽・貯留槽・脱水機などの臭気発生設備を密閉化し、局所排気・集気フードで捕集する
臭気の発生しやすい工程(例:汚泥処理・脱水)に中和・酸化型薬剤を添加する
薬剤投入・攪拌・脱臭装置などの対策を導入し、処理安定性を高める
発生源が不明な場合や対策方法に迷う場合は、無臭元までご相談ください。
より効果的な対策を講じたい場合や、発生源での対応が難しい場合には、工場などの各種事業場から外部への排出経路での対策も検討しましょう。
排気ダクトの清掃や密閉性の向上により、臭気の漏洩や拡散を防止する
排気の方向や高さを調整し、近隣への臭気影響を軽減する
排気ダクトに消臭剤噴霧ユニットを設置し、不快な臭気の拡散を抑制する
無臭元では、こうした排出経路での対策も提供しており、現場ごとの臭気課題に応じた対応設計が可能です。
万が一、特定悪臭物質が発生してしまった場合は、以下の消臭処理技術を活用します。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
消臭剤 |
|
|
燃焼消臭 |
|
|
生物消臭 |
|
|
活性炭 |
|
|
スクラバー |
|
|
各方法にはそれぞれ特徴があり、対象となる物質の種類や濃度、処理量は大きく異なります。発生している悪臭物質に応じて最適な技術を選択する必要があるため、専門家に相談しながら選択することをおすすめします。
特定悪臭物質の測定は、法的な規制基準への適合性確認や対策効果の検証において重要です。測定により、以下のことが可能になります。
自社が規制基準を満たしているかの確認
臭気対策の効果測定
問題の早期発見と改善
特定悪臭物質の測定は、環境省が定める「特定悪臭物質測定マニュアル」に基づいて行われます。以下に、各物質の具体的な測定方法を示します。
悪臭物質の種類 | 分類 | 試料採取 | 採取方法と採取容器 | 保管 | 前処理方法 | 測定方法 | 備考(定量下限値) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンモニア | 敷地境界 | 吸収瓶吸引 | 吸収瓶または試料採取袋 | 低温暗所 | ガスクロマトグラフ法:捕集液を希釈 吸光光度法(インドフェノール青吸光光度法):分析装置(FID)による分析準備 | ガスクロマトグラフ法 吸光光度法 | 1ppm(0.0002ppm) 1ppm(0.0002ppm) 1ppm(0.0005ppm) 1ppm(0.0005ppm) |
硫化水素 メチルメルカプタン 硫化メチル 二硫化メチル | 敷地境界 (排出口・試料採取) | 吸収瓶吸引 (試料採取袋) | 吸収瓶試料採取袋 | 低温暗所 | - | ガスクロマトグラフ法 | 50L(0.00006ppm) |
トリメチルアミン | 敷地境界 | 吸収瓶吸引 | 吸収瓶試料採取袋 | 2,4-DNPH誘導体 | ガスクロマトグラフ法:スポットグラフ分析装置(FTD)による分析準備 | ガスクロマトグラフ法 | 50L(注) |
アセトアルデヒド プロピオンアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド ノルマルバレルアルデヒド イソバレルアルデヒド | 敷地境界 (フェニルヒドラジン) | 捕集管吸引 (アルカリビーズ充填) | 2,4-DNPH誘導捕集袋 常温吸着管 | 低温暗所 常温吸着管 | 高速液体クロマトグラフ法:誘導体化した試料をHPLCで分析 ガスクロマトグラフ法:ガスクロマトグラフ分析装置(FID)による分析準備 | 高速液体クロマトグラフ法 ガスクロマトグラフ法 | 2(0.00005ppm) |
イソブタノール | 敷地境界 | 捕集管吸引 (低温濃縮) | 低温濃縮管 常温吸着管 | 密封・低温保管 | ガスクロマトグラフ法:ガスクロマトグラフ分析装置(FID)による分析準備 | ガスクロマトグラフ法 | 1(0.01ppm) |
酢酸エチル メチルイソブチルケトン | 敷地境界 | 捕集管吸引 (低温濃縮) | 低温濃縮管 常温吸着管 | 密封・低温保管 | ガスクロマトグラフ法:ガスクロマトグラフ分析装置(FID)による分析準備 | ガスクロマトグラフ法 | 1(0.01ppm) |
トルエン スチレン キシレン | 敷地境界 (ステンレス製) | 捕集管吸引 採取袋 (キャニスター) | 低温濃縮管 常温吸着管 試料採取袋 | 暗所 | ガスクロマトグラフ法:ガスクロマトグラフ分析装置(FID)による分析準備 | ガスクロマトグラフ法 | 1(0.01ppm) |
プロピオン酸 ノルマル酪酸 ノルマル吉草酸 イソ吉草酸 | 敷地境界 | 捕集管吸引 | 試料捕集管 (アルカリビーズ充填、試料採取袋) | 密封 | ガスクロマトグラフ法:ガスクロマトグラフ分析装置(FID)による分析準備 | ガスクロマトグラフ法 | 2.5(0.00005ppm) 2.5(0.00002ppm) 2.5(0.00005ppm) 2.5(0.00005ppm) |
参考:環境省「特定悪臭物質測定マニュアル」
上記の表に示すように、特定悪臭物質の測定には物質ごとに異なる試料採取方法と分析方法が必要です。以下の理由から、実際の測定は無臭元などの専門業者への依頼を推奨します。
各種試料採取器具(吸収瓶、捕集管、試料採取袋など)と専用試薬が必要
ガスクロマトグラフ、高速液体クロマトグラフ、吸光光度計などの高度な分析機器が必要
正確な試料採取と分析には専門的な技術と経験が必要
法的に有効な測定データとするには、計量証明事業所での分析が必要な場合がある
定期的な測定・モニタリングを行うことで、基準値超過の早期発見や対策効果の確認が可能となり、継続的な改善につなげられます。
特定悪臭物質(22物質)への対応は、法規制の遵守だけでなく、地域社会との良好な関係構築や事業の安定的な持続・発展のためにも欠かせない取り組みです。まずは自社の状況を正確に把握し、計画的に対策を進めていきましょう。
無臭元では、60年以上にわたって培ってきた臭気対策の技術とノウハウ、現場対応力を活かし、お客さまの臭気問題を解決するためのトータルサポートを提供しています。
特定悪臭物質への効果的かつ経済的な対応には、早期の取り組みが不可欠です。臭気問題でお悩みの方は、ぜひ無臭元までご相談ください。現場の状況に合わせた最適な対策をご提案いたします。