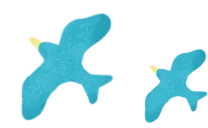

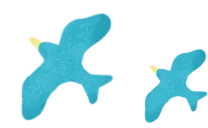

排水処理を伴う工場や下水処理場などの事業場では、BOD(生物化学的酸素要求量)は水質管理の重要な指標のひとつです。
排水基準への適合が法令で求められていることを理解しつつも、「現在の対策では効果が不十分」「基準値を超えてしまう」という課題を抱えている現場は少なくありません。
本記事では、BODの基本的な知識や測定方法を解説するとともに、BOD値が高くなる原因や効果的な対応策もご紹介します。排水管理の改善に向けた参考にしてみてください。
BODとは「Biochemical Oxygen Demand(生物化学的酸素要求量)」の略で、水中の生分解性有機物が微生物によって分解される際に消費される酸素の量を表す指標です。単位は、mg/L(ミリグラム・パー・リットル)です。この数値を管理することで、排水が環境に与える影響度を客観的に評価できます。
BOD値が高いということは、水中に微生物が分解できる有機物が多く含まれていることになります。このような排水が自然水域に流出すると、溶存酸素(DO)を大量に消費してしまうため、水質汚濁や水生生物への悪影響を引き起こすおそれがあります。
一方で、BOD値が低ければ水中の有機物濃度が低いことになるため、排水処理が効果的に機能していると判断することが可能です。
水質汚濁防止法や下水道法では、BODに関する排水基準が定められています。
BODが高いと、水中の溶存酸素(DO)が不足しやすくなり、魚類の死滅や水質の悪化により生態系に大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため、BODは環境水質の健全性を示す代表的な指標として、河川ではBODが用いられています。また、湖沼・海域では主にCOD が環境基準の代表指標として用いられます。
また、排水処理施設の処理効率や運転状況を評価するときも、BODの測定は重要です。処理前後のBOD値を比較することで、設備や薬剤の効果を定量的に把握することが可能です。
BOD値の上昇は、有機物負荷の増加や処理能力の低下を示すサインであり、反対に低下した場合は、負荷軽減や処理能力の改善を意味します。ただし、水温の変化や時間経過による自然減少もあるため、正しく効果を見極めるには、評価時の条件をそろえて比較することが重要です。
BODと似た水質評価の指標として、COD(Chemical Oxygen Demand:化学的酸素要求量)というものがあります。
関連記事:COD(化学的酸素要求量)とは?測定方法と効果的な低減対策をわかりやすく解説
CODは、水中の有機物が酸化分解されるときに必要な酸素量を示す指標です。COD値が高いほど、水が汚れていることになります。
BODとCODの違いは、次のとおりです。
| 項目 | COD | BOD |
|---|---|---|
正式名称 | 化学的酸素要求量 | 生物化学的酸素要求量 |
測定の仕組み | 薬品で有機物を酸化 | 微生物で有機物を分解 |
測定時間 | 約2時間 | 通常5日間(BOD5) |
対象物質 | 有機物全般 | 主に分解しやすい有機物 |
適用場面 | 工場排水、湖沼・海域などの化学的処理対象水 | 河川、下水処理場などの生物処理対象水 |
指標の活用例 | 工場排水など、短時間で水質状況を把握したい場合に適している | 生物処理施設(下水処理場など)の処理性能評価や運転管理に適している |
BODは「微生物が有機物を分解するときに消費される酸素量」を、CODは「薬品(酸化剤)を用いて有機物を化学的に分解するときに消費される酸素量」を示す指標です。
BODは、自然界での微生物による分解過程を模擬して測定されます。そのため、河川や湖沼などの自然環境における水質汚濁の評価に適しています。
一方、CODは、短時間で測定可能なことから、工場排水などの管理用途で広く利用されています。
BODを適切に管理するには、正確な測定と法的基準への理解を深めておくことが大切です。
ここでは、BODの測定方法と管理基準についてみていきましょう。
BOD値が低下している場合は、排水処理が効果的に機能していると判断することが可能です。また、処理前後の差分(BOD除去率)を測ることで、設備・薬剤の効果を客観的に評価できます。
どの程度BODを除去できているかを正確に把握したいときは、以下の計算式を活用しましょう。
BOD除去率(%)=(処理前BOD − 処理後BOD)÷ 処理前BOD × 100
ただし、BOD値が低下する要因には、処理による改善と自然的なものの両方があるため、「本当に設備・薬剤によるものなのか」を見極めることが重要です。
BODが低下する自然的な要因として、以下の4つが挙げられます。
実際の改善効果を知るには、「前後比較」と「条件の固定」が必要です。同一の条件で測定して、正確な処理効果を把握しましょう。
BODの測定は、日本産業規格(JIS)の「JIS K 0102」に規定された国家公定法であり、水質汚濁の環境評価や排水管理において重要な手法です。
測定の大まかな手順は、以下のとおりです。
\[ \mathrm{BOD}\,(\mathrm{mg/L})=\frac{(D_{1}-D_{2})-(B_{1}-B_{2})\times f}{P} \]
各パラメータの意味は下記のとおりです。
上記のように、BODの測定には試料の適切な希釈操作や、培養前後での溶存酸素(DO)の測定など、複雑で正確性を求められる操作が複数あります。そのため、正確な測定には経験や熟練した技術が求められます。
BODに関する法的規制は、排出先により適用される基準が異なります。
まず水質汚濁防止法では、工場や事業場からの排水について一律排水基準として、160mg/L(瞬間値)、120mg/L(日間平均値)が定められています。
また、下水道法においては、公共下水道への排除基準が600mg/L未満とされるのが一般的ですが、自治体ごとに条例で異なることがあるため、地域ごとの基準を確認しておくことが大切です。
さらに、河川などの公共用水域には環境基準(環境基本法)が設けられており、利用目的に応じて1mg/L以下(AA類型)から10mg/L以下(E類型)まで6段階に分類されています。
実務上は、これらの基準値に対して十分な安全率を確保し、余裕をもって運転管理することが望まれます。
BOD値の上昇には、さまざまな要因があります。効果的な対策を講じるには、数値上昇の原因を正確に特定することが大切です。
ここでは、BOD上昇の主な原因を4つの観点から詳しく解説します。
糖類やデンプン、タンパク質などの生物が分解しやすい生分解性有機物は、短期間で高いBOD値を示す傾向があります。とくに、食品製造業や醸造業では、このような原料由来の有機物が主な汚濁源となります。
一方で、化学工業で使用される一部の有機化合物(難分解性有機物)は、微生物の働きによる分解が困難であるため、BOD測定に反映されにくい場合があります。これらの有機化合物は、長期的な水質汚濁の原因となる可能性があるため、「BOD値が低いから大丈夫」とひとつの指標だけで評価することは避け、CODやTOCなど他の水質指標も用いることも検討しましょう。
BODを管理するとき、とくに注意が必要なのが窒素化合物による影響です。肉や魚、大豆などのタンパク質を多く含む原料を使用する工場や、窒素肥料や尿素などを扱う施設では、窒素が酸化される際に酸素を消費する「窒素由来のBOD(N-BOD)」が高まりやすくなります。窒素化合物の分解には多量の酸素が必要で、処理時間も長くかかるため、あわせて処理方法や管理体制の見直しといった対策についてもチェックしておきましょう。
製造工程における排水汚濁の要因として、まず挙げられるのが原材料や製品が排水に混入する「こぼれ」や「漏れ」です。たとえば、配管の破損、バルブの不良、作業時の不注意などによって発生すると、高濃度の有機物が排水に含まれ、BOD値上昇の原因になります。
また、製造設備や容器を洗浄するときの洗浄排水に、高濃度の有機物が含まれることがあります。洗浄頻度や使用する洗剤の種類・使用量によっても負荷が変動するため、必要に応じて洗浄方法の見直しを検討してみましょう。
さらに、製造品目の切り替え時に発生する「切り替え排水」では、一時的に通常より高濃度の汚濁物質が排出される可能性があります。このような短期的な負荷変動が、処理システム全体に影響を与えることは少なくありません。
排水処理システムの問題として、頻繁に起こる問題の一つが、処理能力の超過です。設計上の能力を上回る排水量や汚濁物質が流入した場合や、流入水量・水質の急激な変動などにより、処理能力が著しく悪化することがあります。
とくに生物処理を行うときは、微生物が急激な負荷変動に対応できず、BOD除去率が低下することがあります。加えて、pHや温度の変化、溶存酸素(DO)の不足なども微生物の働きを低下させ、結果的に処理能力そのものが下がる原因となります。
他にも、装置の故障や薬品注入の不良、制御ミスなど、予期せぬトラブルによって、処理性能が一時的に低下し、BOD値が上昇することもあります。BODを安定的に管理するには、適切な運転管理と定期的な設備点検とメンテナンスが欠かせません。
BOD値は、環境や操業条件といった外部要因の影響を大きく受けるため、適切な対応が不可欠です。
まず気をつけたいのが、季節による変動です。
気温が高い夏は微生物の過剰増殖や死滅が起きやすく、逆に冬の低温時期は微生物の働きが低下して処理効率が落ちる傾向があります。BODの管理には、季節に応じた運転管理の調整も不可欠です。
また気象条件の変化も、無視できない要因です。大雨による排水の希釈や処理施設への負荷変動、雨水や地下水の排水処理システムへの流入は、処理性能に大きく影響するため、流入管理やバッファ機能の確保が重要です。
さらに工場の操業パターンにより、一日の中で排水の水質が大きく変動する場合があります生産ピーク負荷時はBOD値が上昇しやすいため、負荷変動に対応できる処理システムの構築と運転制御の最適化が必要です。
BODの低減には、発生源対策から排水処理工程での高度処理まで、さまざまなアプローチがあります。大切なのは、排水の性質や処理目標、コスト、設置条件などを総合的に考慮して、最適な対策を選択・組み合わせることです。
ここでは、BODの効果的な低減対策について紹介します。
発生源対策は、BOD低減において最も効果的なアプローチ方法です。
たとえば、製造工程で発生する原材料のこぼれ・漏れを防止すれば、排水への有機物混入を最小限に抑えられます。そのためには、設備の定期点検や作業プロセスの見直し、従業員教育の徹底が効果的です。
また、高濃度排水と低濃度排水を分離し、高濃度側は回収・再利用または別途処理することで、全体の処理負荷を軽減するというアプローチも有効です。調整槽を用いて排水の水量・水質を均等化し、処理施設への急激な負荷変動を抑制することも効果的な対策です。
重要なのは、排水処理の課題やトラブルが発生している工程を突き止め、原因に合った対策を取ることです。「BOD値が高くなる原因がわからない」「どのような対策が最適かわからない」という場合は、無臭元のように、排水処理に精通したアプローチすべき工程の特定から行える専門家に相談しましょう。
物理的処理は、沈殿や浮上、ろ過などの物理的作用を利用して、排水中の固形物や油分を除去する方法です。設備構成が比較的シンプルで、運転管理が容易な点が大きなメリットです。
たとえば、液体中の個体粒子を遠心力や重力の力で分離する「沈殿分離」は、大容量処理に適しています。ただし、溶解性の有機物(溶解性BOD)への効果は限定的で、沈殿汚泥の適切な処理が必要となる点には注意が必要です。
食品工場や油分を含む排水には、水中に気泡を発生させて浮遊物や油分を吸着させる「加圧浮上分離(DAF)」が有効ですが、設備費やエネルギー消費量が高くなる傾向があるため、事前にコスト・処理負荷・スペース条件などを十分に検討することが重要です。
化学的処理は、凝集剤や中和剤などの薬品を使用して、排水中の汚れを化学反応によって取り除く方法です。汚れの原因となっている物質や浮遊物を薬剤の作用で凝集・沈殿させて水と分離することで、BODの一部(主に懸濁性有機物)を効果的に取り除くことが可能です。
薬品を用いた化学的なアプローチには、短時間で大量に処理できるというメリットがあります。また、生物処理では困難な物質にも対応できる場合がある一方で、BOD成分が完全に溶け切っている場合には、凝集処理の効果が限定的になるため、排水中のBODの性質(懸濁性か溶解性か)を把握したうえでの適用判断が重要です。
生物学的処理は、微生物の代謝活動を利用して水中の有機物(BOD成分)を分解・除去する方法です。自然界における浄化作用を応用したものであり、環境負荷が小さく、持続可能な排水処理手法として広く採用されています。
微生物の働きを用いた生物学的なアプローチには、ランニングコストが比較的低いというメリットがあり、分解しやすい有機物に対しては高い除去効果を発揮します。
一方で、処理に時間がかかることや、水温や水質の変化に敏感な点に注意が必要です。過負荷の場合などに微生物の働きが低下し、処理性能が不安定になる可能性があるため、適切な運転管理の整備が不可欠です。
BOD対策を実施しても期待した効果が得られない場合、まずは以下のような観点で「正しく測定できているか」を確認しましょう。
また、BOD改善効果が出にくい要因として、生物処理では処理効果が現れるまでに数日~数週間かかる場合もあるため、反応遅延を踏まえた評価タイミングを設定することも重要です。即効性を期待しすぎると、正しい判断を誤る恐れがあります。
対策を実施したあとに製造品目の変更や季節の変化によって排水の性状が変わり、せっかくの対策効果が相殺されてしまうケースも珍しくありません。たとえば、夏場に適した処理条件が冬場には適さなくなったり、製品ラインの変更により排水中の有機物の種類が変わったりする場合が挙げられます。
さらに、排水性状に適さない薬剤の使用や、pH・温度・滞留時間などの処理条件が最適化されていない場合も効果が得られにくくなります。
「この対策をすれば必ずBOD値が改善する」という、万能な解決策はありません。まずは、「どの段階で問題が発生しているか」を正確に見極めたうえで、処理プロセス全体の中での最適な対応策を設定していきましょう。
ここでは、無臭元が支援した下水処理場におけるBOD対策の成功事例を紹介します。
同施設では、流入BODが1,000mg/L、T-N(全窒素)が250mg/Lという高濃度排水の処理と、汚泥処分費用の高騰というふたつの課題を抱えていました。
このような状況を受け、無臭元では対策として、生物処理の効率化を目的とした活性微生物製剤「無臭元シュアー100」の導入を提案し、微生物活性の向上による有機物の分解能力を強化し、処理性能の改善を図りました。
その結果、処理水のBOD:5mg/L以下、T-N:5mg/L以下という極めて良好な水質を安定的に維持することに成功。さらに、汚泥量の約25%減量も実現しました。
想定以上の効果が確認されたため、処理状況悪化時の緊急対応として活用しつつ、予算確保と並行して、本格運用への移行が検討されています。
BODは、工場や施設の排水管理において、環境規制への対応や企業としてのコンプライアンスに直結する重要な指標です。BOD値を安定的に管理するためには、排水性状に応じた処理方法の選定や継続的なモニタリングといった対策が欠かせません。
「自社にBOD対策のノウハウがない」という場合は、専門家にも相談しつつ、環境規制への確実な対応と水環境への影響低減を目指していきましょう。
無臭元では、お客さまごとの排水処理にかかる課題や運転条件を丁寧にお伺いし、薬剤や活性微生物製剤を活用した最適なBOD対策をご提案しています。処理プロセスの診断から、改善策の設計・導入、運用時のサポートまで、一貫した支援を通じてお客さまの課題解決をサポートします。
BODをはじめとする水処理の問題・トラブルでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。